家づくりに関係する相続・税金の知識
建てる前に確かめよう、相続・税金のこと。
家づくりに関係する相続・税金のことをあらかじめ知っておこう。
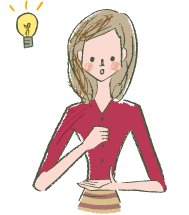
また、新たに住宅を取得することでかかってくる税金と、住宅ローンによる減税の制度もあります。
相続・税金の基礎知識1
親からの贈与
最高2,500万円まで贈与税非課税となる「相続時精算課税制度」。
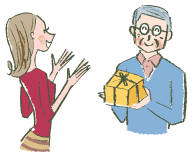
さらに、住宅取得のための資金の場合には、最大で3,000万円(※2)(一定基準を満たす質の高い住宅の場合/一般住宅は2,500万円)まで非課税で、直系尊属であれば親・祖父母の年齢を問わず利用できます。将来の相続税の課税対象にはなりますが、通常の贈与に比べ節税対策としても有効です。
※1 前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。
※2 契約の締結日・消費税率によって非課税枠は変動します。
※平成28年3月現在の情報となります。
相続・税金の基礎知識2
住宅ローン減税
最大500万円が戻ってくる、住宅ローン減税制度をフル活用しよう。

※住宅ローン減税を受けるためには、所得や住宅が一定の条件を満たしている必要があります。
※2016年3月現在の情報となります。
相続・税金の基礎知識3
住宅にかかる税金について
様々な税金があるので、あらかじめ金額を把握しましょう。
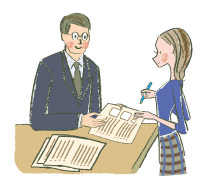
また、不動産を取得する際に行うものとして「建物表示登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」等があります。表示登記には登録免許税は課税されませんが、建物の新築などの「所有権保存登記」、不動産の「所有権移転登記」、住宅ローンの借入れの場合の「抵当権設定登記」など、これらの登記には登録免許税がかかります。
不動産の取得に対しては、不動産取得税が発生しますが、平成30年3月31日までは土地・住宅用建物ともに税率3%の標準税率軽減の特例が適用されます。また、新築住宅にかかる固定資産税については、3年間(マンションは5年間)2分の1となる減額措置の適用期限が平成30年3月31日まで延長されたほか、固定資産税評価額から1,300万円(長期優良住宅の場合/一般住宅は1,200万円)の控除を受けられる特例もあります。
不動産取得によって、これから毎年、固定資産税、都市計画税等を払うことになりますが、こうした住まいに係る税金は特例や軽減措置の内容が随時変わります。どのくらい税金が必要になるか?どのような特例が受けられるか?あらかじめ確かめておくと良いでしょう。
※不動産取得税の控除や税額軽減を受ける為には、住宅や土地が一定の条件を満たしている必要があります。
※掲載の情報は平成28年3月時点の情報です。
関連記事

賃貸併用住宅なら住宅ローンの有効活用。賃貸経営で土地活用を

小規模宅地等の特例で土地の相続税が80%減税に。二世帯住宅のメリット





